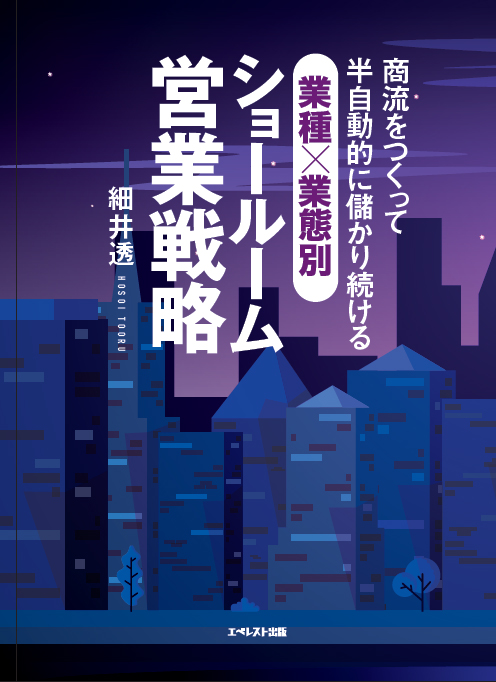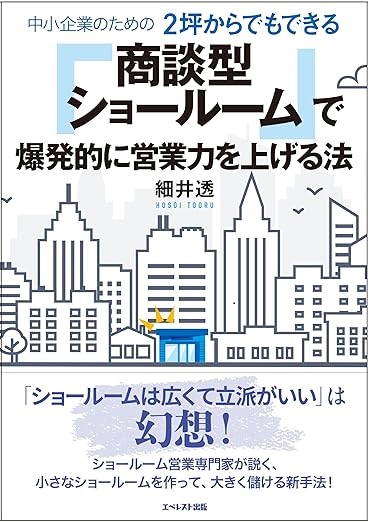第299話 これからの儲かるショールームのつくり方「専門性」
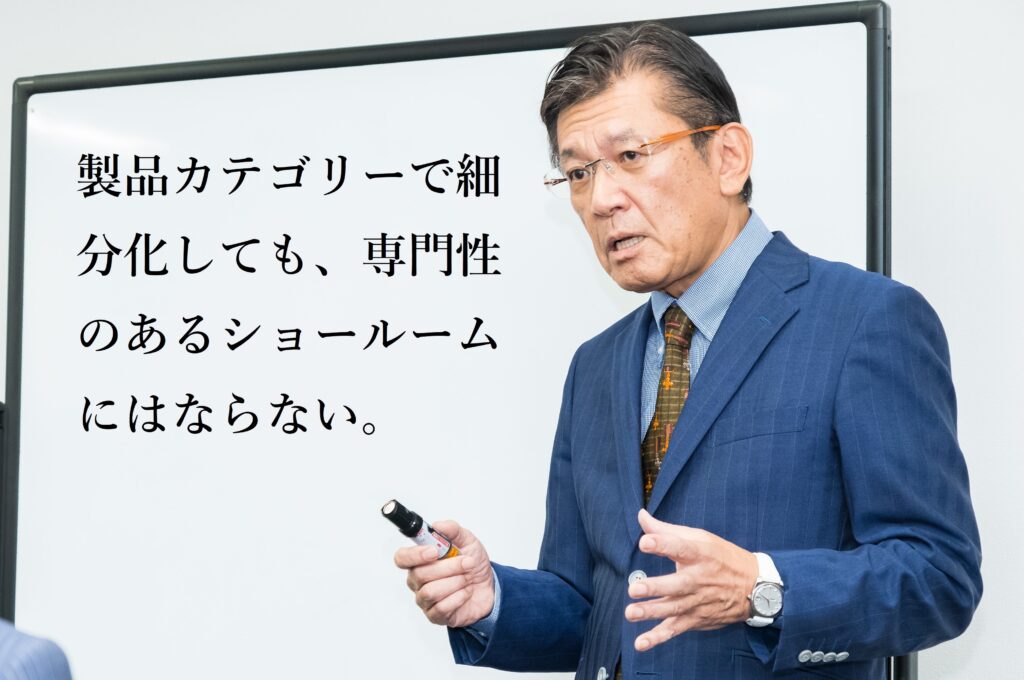
●最新セミナー情報●
「たった2坪でもできる、儲かる商談型ショールーム戦略」セミナー 好評受付中です。
新しいセミナーのカタチ「オンデマンドセミナー」は、いつでもどこでも参加できて好評です。
詳しくはセミナー情報をご覧ください。
●書籍のご案内●
「商流をつくって半自動的に儲かり続ける 業種×業態別 ショールーム営業戦略」
「中小企業のための2坪からでもできる『商談型ショールーム』で爆発的に営業力を上げる法」
好評発売中です。詳しくは書籍のご案内をご覧ください。
前回に引き続き「これからの儲かるショールームのつくり方」について、今回は「専門性」というテーマでお話しします。
「専門」という言葉も、何か魅力を感じさせます。中古軽自動車専門モータースとか、大きな婦人服専門洋品店とか、マンションリノベーション専門工務店とか…。専門と名乗るだけでプロフェッショナルな感じがします。
そもそも中小企業の場合、あれもこれもといって多角化することは、かなり無理があります。少ない経営資源を得意分野に投入し、ニッチな分野で大企業とは異なる土俵で戦うのが常識です。そうであれば、○○専門と名乗って、プロフェッショナル感を出した方がいいに決まっています。
もし、あなたが住宅リフォーム店を経営しているとしたら、ショールームの看板をどのように書きますか? 例えば「住宅リフォーム専門ショールーム」ですか? それとももっと絞って「水回りリフォーム専門ショールーム」ですか?
どちらも「専門」と名乗っていますが、考えてみれば日本全国どこにでもある専門です。誰でも考え付くというか「普通」です。
普通ということは、もうすでに誰かがやっているわけですので、それで大きく儲けようとする方が間違っています。前の人が敷いたレールの上を走っているようなものなので、いくら頑張っても前の列車を追い越すことはできません。もしそうであれば、もっと違う「専門」はないものでしょうか。
前段で示した中古軽自動車専門とか、大きな婦人服専門とか、マンションリノベーション専門とかは何でくくっているかというと、これらは商品の、カテゴリーや分類、種類、区分で分けています。新旧とか、大小とかです。商品のニッチな分野に絞ってビジネスを行うという考えです。
なるほど、分野を絞って細分化すればするほど専門性は高まります。そかしその分、間口は狭くなります。
そうではなく、ビジネス提供の3大欲求とか、人を動かす原動力とか、心の豊かさとかでくくった方が専門性を発揮しやすいですよ、という提案です。もしくは、それらを掛け合わせて専門性を表現できないかということです。かけ合わせることによって、独自の専門性を見つける目的です。
ビジネス提供の3大欲求とは「お金が儲かる」「気持ちがいい」「優越的な立場」のことを言います。これらはビジネスを行う上で、お客様に提供すべき(お客様が望む)基本的な欲求です。
人を動かす原動力とは「驚き」「感動」「楽しさ」「面白さ」です。人は基本的に、常にこのような刺激を求めています。この感情を刺激することにより、購入意欲が増すことは良く知られています。
心の豊かさとは、納得感、満足感、幸福感、笑顔などで表現できます。例えば1杯のラーメンでも、お店の雰囲気や店員の接客態度、注文から提供までの時間などにより、お客様が「ああ美味しかったね。お店はきれいだったし、店員さんは丁寧だし、また来ようね」などと笑顔で話せるとしたら、お客様は満足感や幸福感を得られるでしょう。
このように、専門性のくくり方を変えることにより、独自の専門が出来上がります。誰もまねのできない専門です。
専門性を高めれば商圏は広がります。前段で示したような独自の専門性で勝負すれば、たとえ一般的な製品やサービスであっても、遠方からでも集客できるでしょう。
B2Bビジネスの場合、コストパフォーマンスとか問題解決に役立つか、という視点で購買行動に出ることが多いです。しかしながら、ビジネスは人間同士がやっているわけで、そこには必ず感情が介入します。
ビジネスは、愛嬌や可愛げ、憎めないなどの感情を持ってもらうことで、取引がスムーズにいくことがあります。そのようなときに製品の視点ではなく「心」や「感情」で専門性をくくっていた方がいいに決まっています。
専門のくくり方を変えてみてください。そうすれば、平凡な製品やサービスでも他社とは違った専門が手に入るでしょう。それには独自性と絡めて考えると効果抜群です。
あなたのショールームには専門性がありますか?